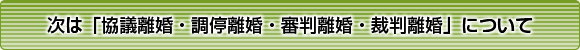離婚届の手続きは、市町村役場にある「離婚届」の届出用紙をもらって記入・押印し、本籍地、または住所地の市町村役場に提出すれば終了です。本籍地以外で離婚届を出す場合は、戸籍謄本も一緒に出しましょう。
それ以外にも、離婚の形態により、離婚届に下記の書類を添える必要があります。
| 離婚届を出す際の添付書類 | |
|---|---|
| 判決離婚のとき | 判決の謄本・確定証明書 |
| 調停離婚のとき | 調停調書の謄本 |
| 審判離婚のとき | 審判書の謄本・確定証明書 |
| 和解離婚のとき | 和解調書の謄本 |
| 認諾離婚のとき | 認諾調書の謄本 |
協議離婚の場合は、上記の書類は必要ありませんが、離婚届の証人欄に、20歳以上の証人2名に記入・押印してもらわなくてはなりません。
また、結婚前の姓に戻さない場合、別途書類(離婚の際に称していた氏を称する届)を、離婚届と同時か、離婚届けの手続きの日から3ヶ月以内に出す必要があります。
離婚届の書き方には、いくつかポイントがあります。
まず、文字は楷書でていねいに書きましょう。
また、書き間違えたときは、修正液などは使わず、二本線で消し、訂正印を押して訂正します。
そのほか、離婚届の書き方のポイントを記しておきます。
| 離婚届の書き方ポイント | |
|---|---|
| 氏名 | 離婚前の氏名を記入。漢字は戸籍に記載されているものを使います。(旧字の場合も) 生年月日は西暦でも元号でもOK。 |
| 住所・世帯主 | 住民登録をしている住所を記入。転居届を一緒に出すなら、新住所と新世帯主で。夜間・休日に手続きする場合は、元の住民票の住所を記入。 |
| 本籍 | 離婚前(現在)の本籍地を記入。戸籍謄本を見ながら、「字」や「番地」なども正確に書きましょう。「1丁目2番地3号」を「1-2-3」などにするのはNG。筆頭者は夫か妻の名前を記入。 |
| 父母の氏名欄 | 実の父母の氏名を記入。離婚している場合や死亡している場合も正確に記入します。 |
| 続き柄 | 長男・長女は「長」、次男・次女は「二」、三男・三女以降はその数字を記入。 |
| 離婚の種類 | 調停や裁判でなければ協議離婚にチェックを入れる。 |
| 結婚前の氏に戻る者の本籍 | 新しい戸籍を作るか、元の戸籍に戻るかにもチェックを。すでに除籍になっている場合は、新しい戸籍を作る。新しい戸籍を作った場合は、筆頭者は自分になる。離婚後に「離婚前の姓」を名乗る場合は空欄に。 |
| 未成年の子の氏名 | 未成年の子どもがいる場合、夫・妻のどちらが親権を持つかを記入。ただし、親権を持ったほうの戸籍に入るわけではないので、子どもを戸籍に入れるときは入籍届が別途必要。 |
| 同居の期間 | 「同居を始めたとき」は、結婚式を挙げた日か、同居を始めた日の早いほうを記入。 |
| 別居する前の住所 | すでに別居しているときは、同居していたときの住所を記入。別居していなければ空欄に。 |
| 別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業 | 該当するところにチェックは必要ですが、職業については国勢調査の年だけでOK。 |
| 届出人の署名・押印 | 必ず本人が署名・押印します。印鑑は認印でもいいですが、ゴム印はNG。 |
| 証人 | 協議離婚の場合は、20歳以上の証人2名に、住所・生年月日・本籍地を記入してもらい、押印をもらいます。夫婦で証人になってもらう場合、それぞれ違った印鑑が必要です。裁判離婚などの場合は、必要ありません。 |